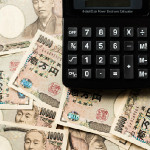MAKの記事一覧
あまり多くはないですが、日本の上場企業の中には米国基準で有価証券報告書等を作成している会社があります。一定の要件を満たす必要がありますが、昭和52年以降特例として認められてきた措置です。現状米国基準で有価証券報告書等を作成している会…
サイドバーに「人気のある記事」あるいは「最近読まれている記事」が表示されているサイトをよく見かけていましたが、Wordpressではプラグインを利用することで容易にそのような表示にできることが分かりました。いくつかプラグインがあるよ…
他の会社を買収した場合の会計上の処理については、企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(企業会計基準適用指針第10号)に従って処理する必要があります。典型的な買収など…
今日(2011年9月1日)の読売新聞朝刊1面に「主婦年金免除基準下げも」という記事が載っていました。記事によると政府は国民年金保険料の支払免除の年収基準を現行の年収130万円から引き下げることを検討する方針を決めたとのことです。…
今回はストックオプションと有価証券届出書(あるいは有価証券通知書)の関係についてです。前提として、ストックオプションは新株予約権の一種なので、金融商品取引法(以下「金商法」とする)上、有価証券に該当します(金商法第2条1項9号)。…
「いったいいくらもらえるの?-遺族年金(その2)」では遺族厚生年金について書きましたが、支給要件等が残っていたので、今回は残りの部分について述べることにします。なお、理解を優先するため表現が厳密でない部分がある点はお断りしておきます。…
前回のエントリで遺族基礎年金について書いたので、今回は遺族厚生年金についてです。前回同様、普通の会社員で厚生年金に加入しているという前提です。公務員の方などは共済に加入されているとおもいますが、共済にも遺族共済年金という制度があり、…
生命保険等に加入する際に一番迷うのは保険金額(保障額)をいくらにするかという点ではないかと思います。保険金額を決める際に、知っておかなければならない事項に遺族年金の存在がありますが、内容についてはほとんど知らないという方が多いのでは…
前回のエントリでは、源泉所得税を納めすぎた場合にどうなるのかについて書きましたが、今回は逆に本来納付しなければならない金額よりも過少に納付していることが明らかになった場合はどうなるかについてです。結論としては、源泉徴収義務者が不足分…
給与計算の担当者は相当神経を使って作業をされていますが、そうはいっても人間のやることなので間違ってしまうことがあります。その結果、源泉所得税を多く計算して納付してしまった場合はどうなるのかが今回のテーマです。税金を多めに納付している…