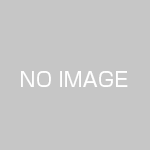国際税務入門(その3)-源泉徴収
今回は国際税務における源泉徴収についてです。前回までと同様「国際税務をマスターしたい!と思ったとき最初に読む本(あいわ税理士法人)」と参考に確認していきます。
源泉徴収制度の役割
これは、国際税務に限ったことではないと思いますが、源泉徴収制度の役割を一言でいえば、税金の取りっぱぐれを防ぐことといえると思います。
しかしながら、国内法人等に比して外国法人等に対する方が、事後的に税金を徴収するのは困難であると考えられるので、税の徴収の実効性を確保するという点においては国際税務における源泉徴収の方が重要度は高いといえるかもしれません。
なお、源泉徴収された税額の取り扱いについては、源泉徴収によって課税関係が終了するケースと税金の前払として確定申告時に精算されるケースがあり、各国の税法に従うことになります。
源泉徴収の対象となる所得
源泉徴収が必要となる所得の範囲は、原則として所得源泉地国の税法により決まりますが、租税条約が存在する場合は、租税条約の内容により影響を受ける可能性があります。
租税条約が締結されていない場合、日本における日本法人が非居住者又は外国法人に支払う所得に対して適用される税率は以下のとおりです(「源泉徴収の仕方 平成26年度版」国税庁)。
| 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の種類 | 源泉徴収の税率 |
|---|---|
| ① 国内において行う組合契約事業から生ずる利益の配分(注1)(所法161一の二) ※ 国内に恒久的施設を有する非居住者及び国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける場合に限る。 | 20.42% |
| ② 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及びその附属設備又は構築物の譲渡による対価(所法161一の三) ※ 譲渡対価の金額が1億円以下で、かつ、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人が支払うものを除く。 | 10.21% |
| ③ 国内において次のような人の人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う非居住者又は外国法人に支払うその人的役務の提供の対価(所法161二) イ 映画や演劇の俳優、音楽家などの芸能人、職業運動家 ロ 弁護士、公認会計士、建築士などの自由職業者 ハ 科学技術、経営管理などの分野に関する専門的知識や特別の技能のある人 | 20.42% |
| ④ 国内にある不動産や不動産の上に存する権利、採石権の貸付け、租鉱権の設定、船舶や航空機の貸付けによる対価(所法161三) ※ 土地家屋等の貸付けによる対価で、その土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものを除く。 | 20.42% |
| ⑤ 日本国の国債、地方債又は内国法人の発行する債券の利子や外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるもの、国内にある営業所等に預け入れられた預貯金の利子等(所法161四) | 15.315% (注2) |
| ⑥ 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当や剰余金の分配などの配当(所法161五) | 20.42% |
| ⑦ 国内において業務を行う者に対する貸付金の利子でその業務に係るもの(所法161六) | 20.42% |
| ⑧ 国内において業務を行う者から受ける次の使用料又は対価でその業務に係るもの(所法161七) イ 工業所有権などの技術に関する権利、特別の技術による生産方法、ノウハウなどの使用料又はその譲渡の対価 ロ 著作権、著作隣接権、出版権などの使用料又はこれらの権利の譲渡の対価 ハ 機械、装置、車両、運搬具、工具、器具、備品の使用料 ニ 上記ロ又はハの資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料 | 20.42% |
| ⑨ 給与等その他人的役務の提供に対する報酬で国内勤務等に基因するもの、公的年金等、退職手当等で居住者期間の勤務等に基因するもの(所法161八) | 20.42% |
| ⑩ 国内において行われる事業の広告宣伝のための賞金、賞品(所法161九) | 20.42% |
| ⑪ 国内において保険業法に規定する生命保険会社、損害保険会社等と締結した保険契約等に基づく年金(所法161十) | 20.42% |
| ⑫ 国内にある営業所等と締結した契約により支払を受ける定期積金の給付補塡金等(所法161十一) | 15.315% |
| ⑬ 匿名組合契約等に基づく利益の分配(所法161十二) | 20.42% |
(注)1「組合契約事業」とは、所得税法第161条第1号の2に規定する組合契約に基づいて行う事業をいいます。
2 振替国債及び振替地方債並びに一定の振替社債等の利子については、一定の要件の下に、その者の所有していた期間に対応する金額の源泉徴収が免除されます(措法5の2、5の3)。
逆に日本の法人が外国法人等から支払を受ける際の源泉徴収税率は、その国の税法によってきまることになります。
一方で、租税条約が締結されている場合は、租税条約で定められている税率を確認する必要があります。仮に、租税条約で定めれらている税率の方が低い場合には、その税率が適用されることになりますが、租税条約の税率の方が高い場合には、上記の税率が適用されることになります。
なお、租税条約による税率が適用される場合は、日本の課税権が租税条約の税率に制限されることになるため復興特別所得税分を源泉徴収する必要はありません。