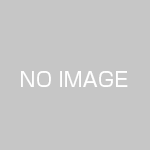欧州で導入される監査事務所のローテーション制度とは?
経営財務3229号のニュースに「欧州で始まる監査事務所の強制交代制」という記事が掲載されていました。
欧州では2016年6月から「監査事務所のローテーション制度(交代制)」が導入されることが決定しているとのことで、継続監査期間の最長は10年とされているそうです。
ただし、EU加盟国に以下の選択肢が認められているとのことです。
- 期間終了後、入札を行って同じ監査事務所が選定された場合は、一回に限りこれを認める(この場合は結局、最長20年継続可能)
- 期間終了後、共同監査として就任する場合は、最大10年の期間を最大14年まで延長できる(この場合は、最長24年まで可能)
入札が要件となっているものの、入札の年度だけ低く報酬を抑えれば最長20年継続可能とも考えられますので、最長20年であればローテーションといってもそれほど影響はないのではないかという気はします。
日本では監督官庁が監査法人が変更になることのほうが異常な状態であると考えているという話を聞いたことがありますので、会計基準がIFRS化しても監査報告書にサインする会計士のローテーションが維持され、欧州のような会計事務所間のローテーションが導入される可能制は現時点では低いのではないかと思います。
長く監査を継続して会社の事業等をよく理解している方が会計上の不正等を発見しやすいのか、事務所自体が変更されることで全く新しい視点で監査を行った方が不正等を発見しやすいのかは一概にはなんともいえませんが、欧州で実施される事務所間のローテーションが有効であるという事例が多くでてくるようであれば、日本の監督官庁も同様の制度を導入することが検討される可能制は考えられます。
なお、当該制度導入後においても、子会社が非上場であれば子会社は上記のローテーションの対象外であるため、日本の企業に与える影響は大きくはないようです。また、「制度の対象がEUを拠点とするEU市場に上場している会社とみられるため、仮にEUと日本の市場双方に上場しているとしても、日本が拠点である日本企業は対象からはずれるとするのが一般的な理解」とのことですので、現時点における日本企業への影響は小さいといえそうです。
日々成